現時点の情報です。最新情報はM5StickC非公式日本語リファレンスを確認してみてください。
概要
前回はデジタル入力でした。今回は「Lesson 6 アクティブブザー」と「Lesson 7 受動ブザー」を説明したいとおもいます。
アクティブブザーとは?
電子ブザーともよばれており、電圧をかけることで音がなるブザーです。
秋月さんだと上記のような商品になると思います。上記は3Vから7Vまでのブザーですが、キットの入っていたのは3.5Vから5.5Vまでのブザーでした。
ESP32だと3.3Vなので、ちょっと電圧が足りないですがなんとか音はでると思います。
受動ブザーとは?
パッシブブザーや圧電スピーカーと呼ばれるブザーです。電圧を変化させることで音がなるブザーです。
秋月さんだと上記のような商品になると思います。
電子ブザーと圧電スピーカーの違いとは?
電子ブザーは電圧をかけると音がなる単純なブザーです。一方圧電スピーカーは、普通のスピーカーと同じように、音声波形を入力することで音がなるスピーカーです。
単純な音を出すのは電子ブザーの方が制御がかんたんですが、複雑な音を出す場合には圧電スピーカーを使う必要があります。
接続方法
電子ブザーも圧電スピーカーも、プラスとマイナスにわかれていますのでプラスをGPIO26、マイナスをGNDに接続します。
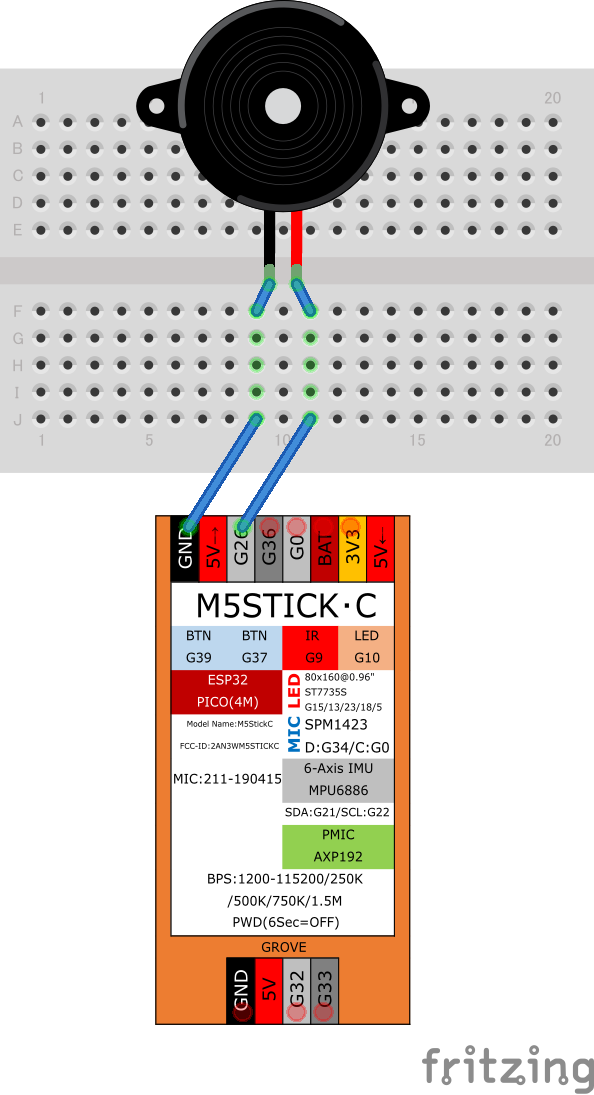
電子ブザーのサンプルスケッチ
//www.elegoo.com
//2016.12.08
int buzzer = 26; // GPIO26の電子ブザーのプラスを接続する
void setup()
{
pinMode(buzzer, OUTPUT); // 出力モードに変更
}
void loop()
{
unsigned char i;
while (1)
{
// 音を鳴らしてみる
for (i = 0; i < 80; i++) {
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(1); // 1ミリ秒待機
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(1); // 1ミリ秒待機
}
// 違う音を鳴らしてみる
for (i = 0; i < 100; i++) {
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(2); // 2ミリ秒待機
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(2); // 2ミリ秒待機
}
}
}
電子ブザーは電圧をかけると音がなるので、非常に扱いがかんたんです。ONにしっぱなしでもいいですし、ONとOFFの間隔を調整することで音を変えることができます。
圧電スピーカーのサンプルスケッチ
//www.elegoo.com
//2016.12.08
#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978
// メロディーデータ
int melody[] = {
NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5, NOTE_A5, NOTE_B5, NOTE_C6
};
int duration = 500; // 500ミリ秒
void setup()
{
// 初期化
pinMode(26, OUTPUT);
ledcSetup(1, 12000, 8);
ledcAttachPin(26, 1);
}
void loop()
{
for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
// 指定した周波数を出力して0.5秒待機
ledcWriteTone(1, melody[thisNote]);
delay(duration);
// 音を止める
ledcWriteTone(1, 0);
// 音の間隔を1秒あける
delay(1000);
}
// 2秒経過したら再度鳴らす
delay(2000);
}
ちょっと音の宣言が長いですが、処理はたいしたことはしていません。
上記のPWM出力を使って周波数を生成しています。音を聞いてもらえればわかりますが、それほどきれいな音ではなりません。DAC出力を使って、普通のスピーカーを接続するともう少し普通の音になると思います。
まとめ
かんたんに利用できますが、音質はいまいちです。簡易的に音を出すのには適していますので、いろいろ変更して楽しんでみてください。

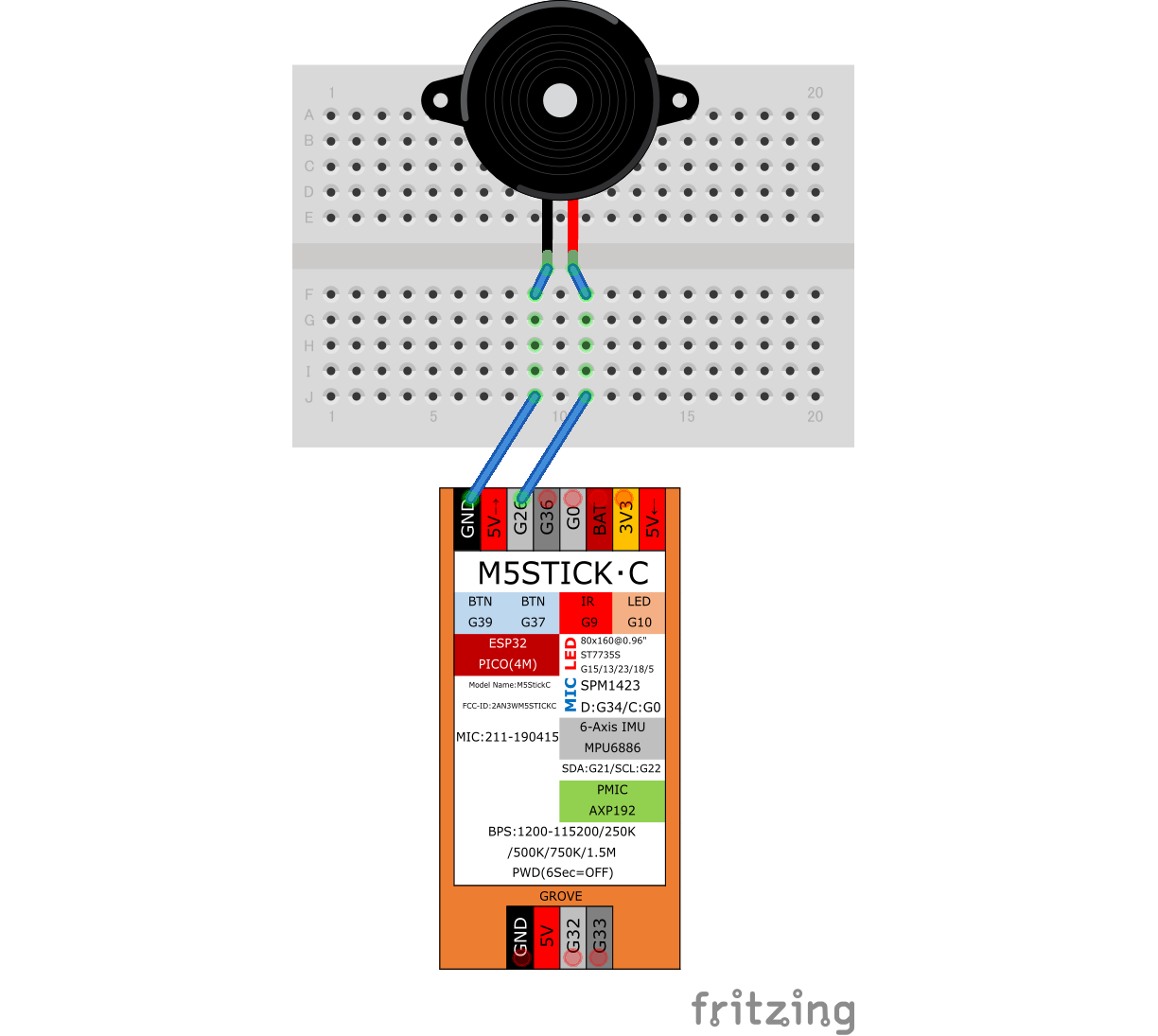
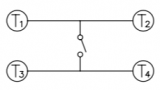




コメント